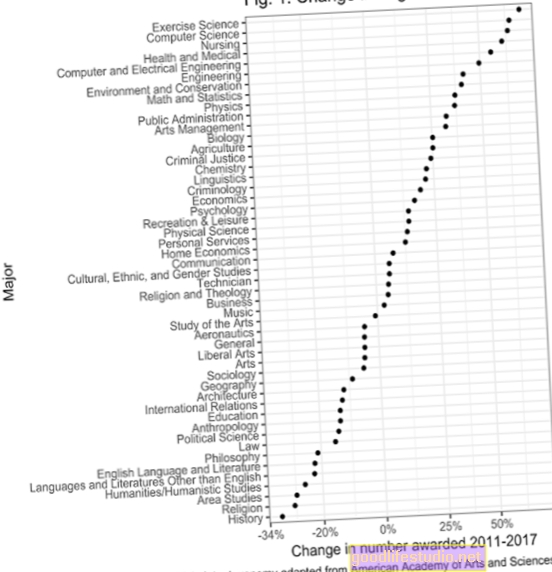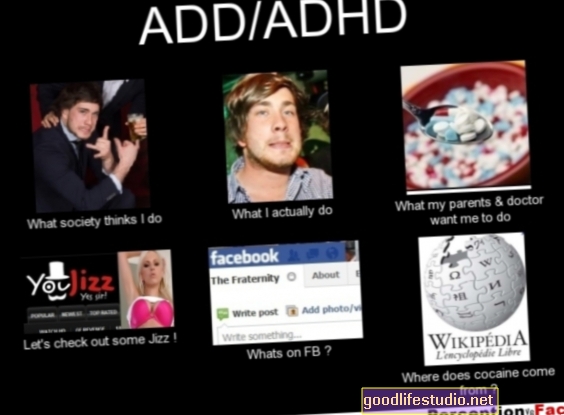ADHD兆候のあるPre-K子供の異常な脳成長
脳イメージングを使用した新しい研究により、注意欠陥多動性障害(ADHD)の初期症状を示す非常に幼い就学前の子供の間で脳の発達に違いが見つかりました。
ADHDは最も一般的な小児の行動診断であり、約200万人の子供に影響を与えます。障害は、不注意、多動性および衝動性によって特徴付けられます。
研究者によると、4歳までに、40%もの子どもたちが、両親や幼稚園の教師に注意を向けるのに十分な問題を抱えています。専門家は、この観察が重要であるのは、症状が幼児期に始まる子供は学業の失敗や学年の重複のリスクが高いためです。
このリスクがあるため、研究者は、診断の過程で早期に障害を特定することで、早期の介入が可能になり、長期的な転帰を助けると考えています。
以前の磁気共鳴画像法(MRI)の研究では、ADHDに関連する脳の違いについていくつかの洞察が得られましたが、これらは7歳以上の子供に焦点を当てていました。
現在の研究では、ADHDの症状がある場合とない場合の両方の就学前児(4歳と5歳)の脳の画像を調査し、特に皮質および大脳基底核の体積と脳のこれらの特定の領域のサイズを調べました。
研究者らは、26人の未就学児(13人がADHD症状を呈し、13人が未発症)の高解像度MRI脳画像を分析し、尾状核の違いを発見しました。これは、認知および運動制御に関連する脳の皮質下領域の小さな構造です。
レビューで、研究者らは、ADHD症状のない子供と比較して、ADHD症状のある子供が尾状核の体積を大幅に減少させていることを発見しました。さらに、これらの尾状核の量は、親の過活動/衝動性症状の評価と有意に相関していた。ただし、皮質ボリュームは症状の重症度とは関連していませんでした。
研究者たちは、大脳基底核の発達、特に尾状核の発達の違いが、ADHDの早期発症症状を示す子供たちの間で重要な役割を果たすように見えると結論付けました。
「臨床的に、この異常な脳の発達は、学校における認知の課題と問題に寄与するADHDの症状のステージを設定します」と、筆頭著者のマーク・マホーン博士は述べました。 「就学前の年に注意の問題を示している子供の以前の特定と治療は、長期的にADHDの影響を最小限に抑えるかもしれません。」
研究者は対象となる子供の脳の発達を引き続き追跡し、異常が持続するか、年齢とともに退行するかを判断します。
出典:ケネディクリーガー研究所